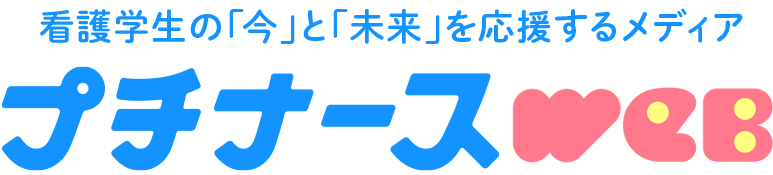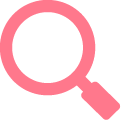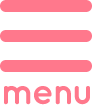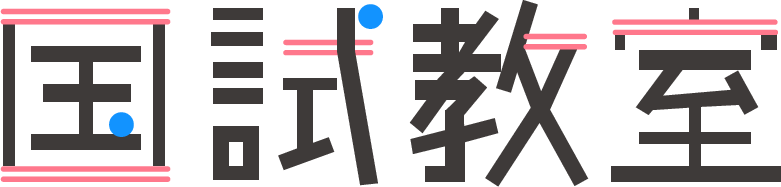プチナース国試部
過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!
- <no.35>第107回午前問題89
- 精神科病院で行動制限を受ける患者への対応で正しいのはどれか。2つ選べ。
- 行動制限の理由を患者に説明する。
- 原則として2名以上のスタッフで対応する。
- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
- 精神保健指定医による診察は週1回とする。
- 12 時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
解答1 行動制限の理由を患者に説明する。 解答2 原則として2名以上のスタッフで対応する。
1.行動制限の理由を患者に説明する。
→◯ 患者の自由の制限が必要とされる場合においては、その旨を患者にできる限り説明して制限を行うよう努めると定められており(昭和63年厚生省〈当時〉告示)、行動制限の理由を患者に説明するのは正しいです。
2.原則として2名以上のスタッフで対応する。
→◯ 法律では規定されていませんが、2名以上のスタッフで対応することは事故防止やルール遵守のために重要なことです。
3.信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
→× 表1のような行動の制限は行ってはならないとされているため、誤りです。
4.精神保健指定医による診察は週1回とする。
→× 「指定医は、隔離、身体的拘束が1回の指示で1週間を超えないよう適時診察し、指示を出す」(診察が1週間に1回とは述べられていません)と規定されていますが、指定医かどうかに関係なく診察については以下のようにされています。 よって、誤りです。
|
①主治医は、1日に1回以上、行動制限を行っている患者を診察し、その所見及び行動制限継続の要否を診療録に記載する
②当直医は、隔離、身体的拘束中の患者の状況を把握するとともに、1日に1回以上、行動制限を行っている患者を診察する。また、その所見などについて診療録に記載する
③隔離解除の指示は指定医ではない医師もできる
④隔離を行っている閉鎖的環境の部屋にさらに患者を入室させることはできない。また、すでに患者が入室している部屋に隔離のためほかの患者を入室させることはあってはならないものとする
|
→× 表2のような場合に該当すると認められる患者に対して、隔離以外によい代替方法がない場合に行われます。行動の制限を必要と認めた指定医(12時間以内の隔離の場合は医師)は診療録に氏名を記載すると規定されており、時間の長さにかかわらず看護師が行動制限するという判断をすることはできません。
表1 法令で禁じられている行動制限
| ①信書の発受の制限
②都道府県又は指定都市及び地方法務局その他人権擁護に関する行政機関の職員との電話
③患者の代理人である弁護士との電話
④都道府県等及び地方法務局その他の人権擁護に関する行政機関の職員との面会
⑤患者の代理人である弁護士及び患者又は保護者の依頼により患者の代理人となろうとする弁護士との面会
|
表2 隔離の実施が検討される場合
|
①他の患者との人間関係を著しく損なう恐れがある等、その言動が患者の病状の経過や予後に著しく悪く影響する場合
②自殺企図または自傷行為が切迫している場合
③他の患者に対する暴力行為や著しい迷惑行為、器物破損行為が認められ、他の方法ではこれを防ぎきれない場合
④急性精神運動興奮等のため、不穏、多動、爆発性などが目立ち、一般の病室では医療または保護を図ることが著しく困難な場合
⑤身体合併症を有する患者について、検査および処置のため、隔離が必要な場合
|
正答につながるポイント!
行動制限とは隔離、身体的拘束と通信や面会の制限のことをいいます。また、行動制限に関する法的な規定では、精神保健指定医とそうでない医師の2つの場合があるので注意しましょう。
国試対策のポイント!
精神看護学を学習するうえでの「柱」は、以下の4つです。それぞれのポイントをおさえましょう。
①疾患とその症状を、きちんと理解する(例:観念奔逸)
②薬物についてまとめる(例:薬物の種類、作用型)
③患者さんの状況に応じてどのように対応するか、過去問から理解する
④社会福祉や精神看護学で使われる語を覚える(例:スティグマ、デブリーフィング など)
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)