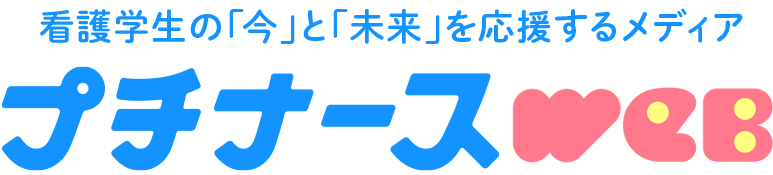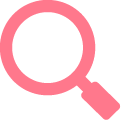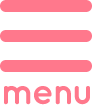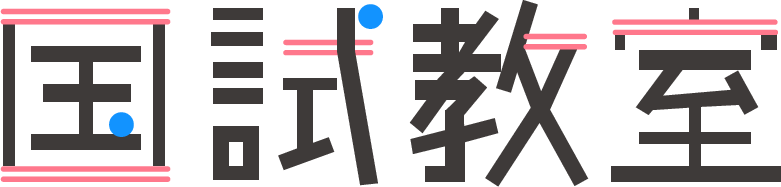プチナース国試部
過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!
- <no.34>第107回午後問題58
- 母子保健施策とその対象の組合せで正しいのはどれか。
- 育成医療――――――結核児童
- 養育医療――――――学齢児童
- 健全母性育成事業――高齢妊婦
- 養育支援訪問事業――特定妊婦
解答4 養育支援訪問事業―特定妊婦
1.育成医療―結核児童
→× 結核児童は児童福祉法に基づく結核児童療育給付(試験では「療育の給付」と呼ぶこともある)※であり、誤りです。結核児童療育給付は指定療育機関で行う治療のうち、表1が対象となります。なお、療育の給付とは別の制度である育成医療(「自立支援医療」と呼ぶこともある)は児童福祉法により行われてきた施策でしたが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉に一元化されました。対象は、身体に障害のある児童、またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できる場合に、指定医療機関において医療を受ける場合に給付(自立支援医療費の給付)が受けられます。事前申請を原則とし、申請先は市町村となっています。
2.養育医療―学齢児童
→× 養育医療は母子保健法にもとづき、身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんに必要な医療に対する医療費が助成されます(表2)。よって、学齢児童は誤りです。
3.健全母性育成事業―高齢妊婦
→× 健全母性育成事業は対象が思春期の男女であり、誤りです。個別相談事業・集団指導事業がありますが、国の補助事業的な位置づけであったため、近年は他の事業(次世代育成支援対策交付金など)に組み込まれたり、廃止したりしている市町村が多いという実態があります。
4.養育支援訪問事業―特定妊婦
→◯ 養育支援訪問事業は、次世代育成支援対策交付金によるもので、養育支援が特に必要であると判断した家庭(特定妊婦※※も含む)に対して、保健師、看護師、助産師、保育士などが継続してその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行います(表3)。
※※特定妊婦とは、出産後の子どもの養育について出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のこと
表1 結核児童療育給付
| ①診察
②薬剤又は治療材料の支給 ③医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 ④病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤移送
⑥学習に必要な物品の支給(学習用品) ⑦療養生活に必要な物品の支給(日用品) |
表2 養育医療の対象
①出生時体重が2,000g以下の乳児
②①以外の乳児で、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
| 対象となる症状 |
|
(ア)一般状態 a 運動不安、痙攣があるもの b 運動が異常に少ないもの (イ)体温が摂氏34度以下のもの (ウ)呼吸器、循環器系 a 強度のチアノーゼが持続するもの及びチアノーゼ発作を繰り返すもの b 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの c 出血傾向の強いもの (エ)消化器系 a 生後24時間以上排便のないもの b 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの c 血性吐物、血性便のあるもの (オ)黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
表3 養育支援訪問事業の家庭内での育児に関する具体的な援助
|
●産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助 ●未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導 ●養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導 ●若年の養育者に対する育児相談・指導 ●児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援 |
正答につながるポイント!
古典的な内容ではありますが、根拠となる法令の変化(例:障害者自立支援法→障害者総合支援法)などもあります。下表に対象や根拠法令をまとめたので、確実な知識にしていきましょう。
母子を対象とする保健施策
| 結核児童 | 未熟児 | 思春期の男女 | 支援が必要な家庭 | |
| 名称 | 結核児療育医療 | 未熟児養育医療 | 健全母子育成事業 | 養育支援訪問事業 |
| 内容 | 結核の児童に対し、学習品・日用品を支給するとともに医療費の自己負担分を一部給付 | 未熟児に対する入院医療費についての医療保険の一部負担分を給付 | 思春期保健教育事業が中心。保健や育児等に関する普及や啓発 | 保健師、看護師、助産師、保育士などが継続してその居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う |
| 対象者 | 結核罹患児※ | 1歳未満の未熟児※ | 思春期の男女 | 養育支援が特に必要であると判断した家庭 |
| 根拠・法令 | 児童福祉法 | 母子保健法 | ― | 児童福祉法 |
国試対策のポイント!
育成医療と療育医療などの違いは一時期よく出題されていました。近年復活し、やや深い内容が問われるようになってきています。
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)