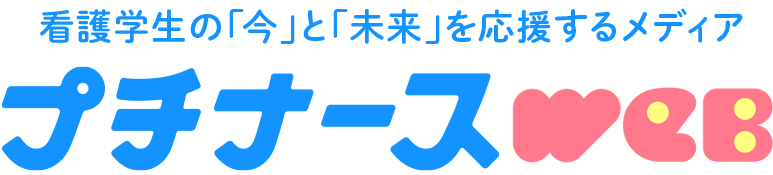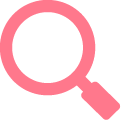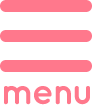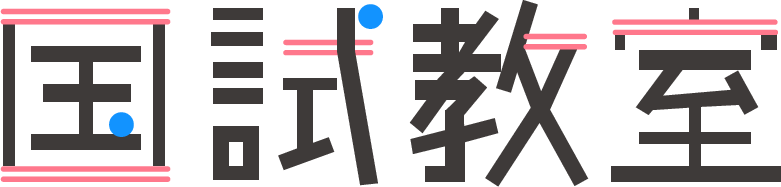プチナース国試部
過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!
- <no.31>第107回午前問題50
- Aさん(70歳、女性)。夫(72 歳)と2人暮らし。慢性腎不全のため腹膜透析を行うことになった。認知機能や身体機能の障害はない。腹膜透析について説明を受けた後、A さんは「私のように高齢でも自分で腹膜透析をできるのか心配です。毎日続けられるでしょうか」と話した。
Aさんへの対応で最も適切なのはどれか。
- 「誰でも簡単にできます」
- 「ご家族に操作をしてもらいましょう」
- 「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」
- 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」
解答4 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」
1.「誰でも簡単にできます」
→× 70歳のAさんに認知機能や身体機能の障害はないという情報がありますが、毎日清潔操作ができるかどうかは個別性があることだと思います。よって1のように「誰でも簡単にできます」と言い切ってしまうのが適切とは言えません。
2.「ご家族に操作をしてもらいましょう」
→× 2人暮らしであり、72歳の夫の状況については情報がなく、判断するのは困難です。
3.「訪問看護師に毎日見守ってもらいましょう」
→× 毎日の訪問看護が医療保険や介護保険で可能かどうか判断できませんし、透析液の交換のたび(CAPD*で行うのであれば1日2~4回の交換が必要となる※ )に見守ってもらうのは現実的ではありません。
4.「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみましょう」
→◯ 「同年代で腹膜透析をしている人の体験を聞いてみる」というステップのあとにAさんが考え、行動することで今後必要な援助がわかってくるはずです。
※CAPDのほかに夜間を利用して行うAPD*があり、透析液交換や接続のための専用の機器がある。
*【CAPD】continuous ambulatory peritoneal dialysis
*【APD】automated peritoneal dialysis:自動腹膜透析
正答につながるポイント!
平成30年版出題基準に加わった中項目「慢性期の高齢者への看護」の小項目「慢性期の高齢者の援助」に該当する問題です。まず問題を解くにあたっては、腹膜透析がどのようなものかを理解している必要があるでしょう。 腹膜透析では専用のカテーテルを腹腔内に留置する手術をします。腹膜透析の導入には、例として次のパターンがあります。
●手術と腹膜透析についての指導までを入院期間中に3~4週間程度かけて行うパターン
●カテーテルの埋め込み手術のために約1週間入院してから退院後に腹膜透析の指導を数週間外来で行い、再び入院してカテーテルを腹腔内から取り出して出口部の手術を行うパターン
腹膜透析で重要なことは、カテーテル出口部の皮膚の管理と透析液(カテーテル接続を含む)を清潔に扱えることです(表)。以上のことを総合して問題を解きましょう。
国試対策のポイント!
高齢者に限らず、自己管理に不安がある人への支援は「たぶんできるだろう」では進めることができません。十分な情報のもとでの自己決定とエンパワメントの視点を忘れないようにします。
表 腹膜透析で重要なこと
| カテーテル出口部の皮膚の管理 | ●石けんでカテーテルのまわりの皮膚を洗うが、強くこすらないように注意する ●出口部の周囲を触り、痛みがないかを確認する |
| 透析液を清潔に扱う | ●不潔に扱うと、腹膜炎などを生じさせる危険がある |
| 腹膜透析ができる期間 | ●一般に5~8年とされている ●血液透析に比べて残腎機能の保持にはプラスだが、腹膜は疲弊して傷んでいく。その後はほかの透析方法や腎臓移植に切り替える必要がある |
| 合併症 | ●感染、カテーテル位置異常、腹膜炎、腰椎ヘルニア、被嚢性腹膜硬化症など |
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)