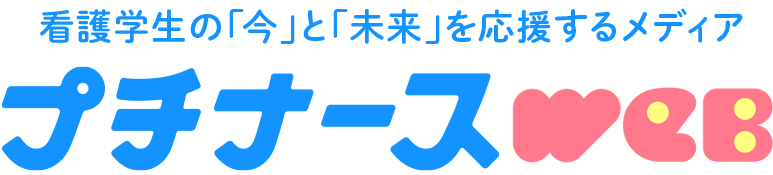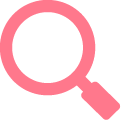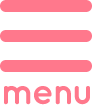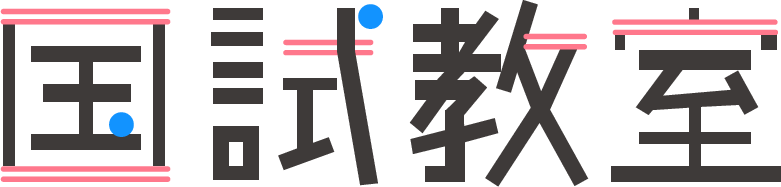プチナース国試部
過去問をもとに、正答につながるポイント、国試対策のポイントをていねいに解説!
- <no.30>第106回午前問題69
- Aさん(65歳、女性)は、夫と実父との3人暮らしである。脊柱管狭窄症の術後、地域包括ケア病棟に入院中である。退院後は自宅に戻り室内で車椅子を利用する予定である。Aさんの障害高齢者の日常生活自立度判定基準はB-1である。
看護師による家族への指導で最も適切なのはどれか。
- 家族の生活習慣を中心に屋内環境を整備する。
- 夜間の車椅子によるトイレへの移動は制限する。
- 退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。
- ベッドから車椅子への移動介助にリフトの導入を勧める。
解答3 退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。
1.家族の生活習慣を中心に屋内環境を整備する。
→× 家族の生活習慣も考慮しますが、中心にするのはAさん本人の生活習慣です。「最も適切」とは言えません。
2.夜間の車椅子によるトイレへの移動は制限する。
→× 住環境が整い、Aさんも慣れれば夜間にトイレに移動することも可能かもしれません。自宅に戻る前の指導から移動を制限する、と言いきってしまうのは適切とは言えません。
3.退院後の生活の課題に応じて福祉用具を選定する。
→〇 この選択肢には条件も制限もなく、療養生活を支えるために必要な指導です。これが答えです。
4.ベッドから車椅子への移動介助にリフトの導入を勧める。
→× 住環境の情報がなく、夫の介護能力も不明なことから、必要か判断することは難しく、「最も適切」とは言えません。
正答につながるポイント!
少し在宅看護論よりの問題ですね。障害高齢者の日常生活自立度〈寝たきり度〉判定基準(表)は必ずチェックしましょう。問題のAさんは、B-1「車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う」状態となります。 退院後は自宅に戻り、室内で車いすを利用する予定であることを念頭に置いて指導を考えます。
国試対策のポイント!
「障害高齢者の日常生活自立度判定基準」は「寝たきり度」の判定基準とも言われます。最も自立しているのがクラスJ(“Jiritsu”の頭文字)、最も自立していないのがCとなります。
表 障害高齢者の日常生活自立度〈寝たきり度〉判定基準
| 生活自立 | ランクJ | 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する ❶交通機関等を利用して外出する ❷隣近所へなら外出する |
| 準寝たきり | ランクA | 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない ❶介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する ❷外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
| 寝たきり | ランクB | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ ❶車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う ❷介助により車いすに移乗する |
| ランクC | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する ❶自力で寝返りをうつ ❷自力では寝返りもうてない |
平成3年11月18日 老健第102-2号 厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知を改訂
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)