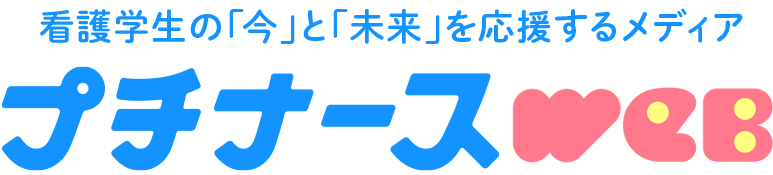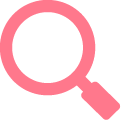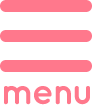必修予想問題
予想問題で必修問題対策。あわせて知っておきたい知識も解説!
- <no.14>平均余命
- 第二次世界大戦後の、男性の平均寿命の延びで最も近いのはどれか。
- 17年
- 22年
- 27年
- 32年
解答4 32年
昭和22(1947)年の平均寿命は男性50.06年、女性53.96年であり、令和2(2020)年は男性81.56年、女性87.71年であった(表1)。つまり男性は約32年、女性は約34年寿命が延びたことになる(4.○)。
平均寿命は0歳の平均余命であるので、現在生存している人はそれぞれ年齢に応じた平均余命があることに注意する。たとえば、令和2(2020)年時点での40歳の平均余命は男性42.50年、女性48.37年で、65歳だと男性19.97年、女性24.88年となる。
表1 戦後における平均寿命の推移(抜粋、単位:年)
●従来の「男性の平均寿命はどれか」という問いから発展して問われる可能性もある。
| 男 | 女 | ||
| 昭和22(1947)年 | 50.06 | 53.96 | |
| 昭和35(1960)年 | 65.32 | 70.19 | 女性が70年を超える |
| 昭和46(1971)年 | 70.17 | 75.58 | 男性が70年、女性が75年を超える |
| 昭和59(1984)年 | 74.54 | 80.18 | 女性が80年を超える |
| 昭和61(1986)年 | 75.23 | 80.93 | 男性が75年を超える |
| 平成25(2013)年 | 80.21 | 86.61 | 男性が80年を超える |
| 令和2(2020)年 | 81.56 | 87.71 |
上の問題は平均寿命の変遷でしたが、死因の変化もあわせてみてみましょう。
①全結核が死因の第1位だった時代(1947~1950年)
戦後の死因統計が始まった1947年から1950年までは全結核が死因の第1位であり、厚生省(当時)は1951年に結核予防法を大きく改正し、BCG*接種・健康診断・適正医療の普及を3本柱として対策しました。
それにくわえ、ストレプトマイシンなどの治療薬の普及や食生活の改善による栄養状態の向上などもあり、結核による死亡は減っていきます。1953〜1956年が4〜5位となった以降、死因の上位5つからも姿が消え、1986年には死亡率が3.4にまで低下しました(1947年の死因第1位のときには、死亡率は187.2でした)。
②脳血管疾患が死因の第1位だった時代(1951~1980年)
脳血管疾患は1951年から1980年までと長期に渡り、日本人の死因の第1位でした。また1958年から1980年までは第1位:脳血管疾患、第2位:悪性新生物、第3位:心疾患の時代となりました。
③悪性新生物は1981年からずっと第1位のまま
悪性新生物は1981年からずっと第1位です。第2位が心疾患である時期も1985年から2021年まで(1994年・1995年のみ脳血管疾患が第2位)と続いています。最近では高齢化社会を反映して2018年に老衰が第3位になりました。
なお、1994年と1995年の心疾患の減少は、新しい死亡診断書(死体検案書)における「死亡の原因欄には、疾患の終末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないで下さい」という注意書きが周知された影響によるものと考えられています。一方、1995年に脳血管疾患が増加しましたが、これは平成7年1月からのICD-10*の適用による死因選択ルールの明確化によるものと思われます。
表1で取り上げた年度を中心に、死因順位の推移を示します(表2)。
*【BCG】bacillus Calmette Guerin:カルメット・ゲラン桿菌
*【ICD-10】international classification of disease-10:国際疾病分類第10版
表2 死因順位別にみた死亡率の推移
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 備考 | ||||
| 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 | 死因 | 死亡率 | ||
| 昭和22(1947)年 | 全結核 | 187.2 | 肺炎及び気管支炎 | 174.8 | 胃腸炎 | 136.8 | 第二次世界大戦は1945年に終わった |
| 昭和35(1960)年 | 脳血管疾患 | 160.7 | 悪性新生物 | 100.4 | 心疾患 | 73.2 | 女性の平均寿命が70年を超える |
| 昭和46(1971)年 | 脳血管疾患 | 169.6 | 悪性新生物 | 117.7 | 心疾患 | 82.0 | 男性の平均寿命が70年、女性が75年を超える |
| 昭和59(1984)年 | 悪性新生物 | 152.5 | 脳血管疾患 | 117.2 | 心疾患 | 113.9 | 女性の平均寿命が80年を超える |
| 昭和61(1986)年 | 悪性新生物 | 158.5 | 心疾患 | 117.9 | 脳血管疾患 | 106.9 | 男性の平均寿命が75年を超える |
| 平成25(2013)年 | 悪性新生物 | 290.3 | 心疾患 | 156.5 | 脳血管疾患 | 94.1 | 男性の平均寿命が80年を超える |
| 平成30(2018)年 | 悪性新生物 | 300.7 | 心疾患 | 167.8 | 老衰 | 88.2 | 死因の第3位が老衰になる |
| 令和2(2020)年 | 悪性新生物 | 306.6 | 心疾患 | 166.6 | 老衰 | 107.3 | |
〈引用・参考文献〉
1.厚生労働省:平成21年(2009) 人口動態統計(確定数)の概況.第7表 死因順位(第5位まで)別にみた死亡数・死亡率(人口10万対)の年次推移.
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth7.html
2.厚生労働省:令和3年(2021)人口動態統計(確定数)の概況.5-12 死因(死因年次推移分類)別にみた性・年次別死亡数及び死亡率(人口10万対).
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei21/index.html
3.厚生労働統計協会:国民衛生の動向 2022/2023.
4.結核研究所:結核研究所の沿革.
https://jata.or.jp/outline_history.php(いずれも2023.5.19アクセス)
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)