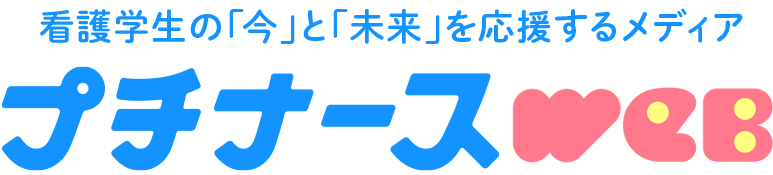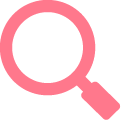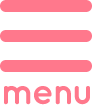必修予想問題
予想問題で必修問題対策。あわせて知っておきたい知識も解説!
- <no.08>血液
- フィブリノゲンを産生するのはどれか。
- 胸 腺
- 肝 臓
- B細胞
- 血管内皮細胞
解答2 肝 臓
フィブリノゲンは肝臓で産生される凝固因子で、血栓の骨格となるフィブリンの前駆体タンパクである(2.〇)。血小板凝集にもかかわる。血液検査としては200~400mg/dLが基準値である。
1.× 胸腺には、T細胞の前駆細胞が移行してきてT細胞に分化・成熟する。
3.× B細胞からは形質細胞が分化し、免疫グロブリンを産生する。
4.× 血管内皮細胞は一酸化窒素(NO*)やエンドセリンなどの多数の血管作動性物質のほか、状況に合わせて凝血促進分子、抗血栓因子などを産生する。肺の血管内皮細胞はアンジオテンシンⅠ変換酵素(ACE*)を産生する。
*【NO】nitric oxide
*【ACE】angiotensin converting enzyme
①血液中のタンパク質としてのフィブリノゲン
血液は血漿と血球成分(赤血球、白血球、血小板)から成り立ち、血漿中のタンパク質は、フィブリノゲン、グロブリン、アルブミンが大部分を占めます。血漿からフィブリノゲンを含む凝固因子を除いたものは血清ですが、血清中のタンパク成分も微量なものを含むと100種類以上あります。
血漿中のタンパク成分の変動においては、量的に多いグロブリンやアルブミンの増減が大きく影響します。タンパク分画という検査で、疾患によってタンパク成分の特徴的な変動(量的、質的)が生じていないかを調べます。
②血液凝固因子としてのフィブリノゲン
血液凝固因子はタンパク質、酵素、イオンなどで、15の因子があります。そのうち12の因子にはローマ字のⅠからXⅢまで(Ⅵは欠番)がつけられています。フィブリノゲンは第Ⅰ因子ですが、血液凝固のプロセスでは最後にはたらきます。
血液凝固は二次止血にあたります(血小板による止血が一次止血)。傷害された血管内皮細胞は第Ⅲ因子(組織因子)を出し、これに血液が触れることで凝固反応が始まります。凝固因子が次々と反応してトロンビンが形成され、これがフィブリノゲンをフィブリンに転換することで強固な血栓ができます。
〈引用・参考文献〉
1.浅野嘉延:検査まるわかりガイド.照林社,東京,2020.
2.飯野京子 著者代表:系統看護学講座 専門分野 成人看護学[4] 血液・造血器.医学書院,東京,2019.
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)