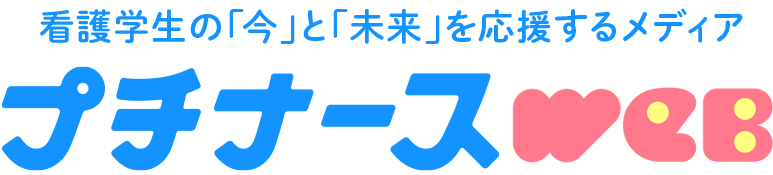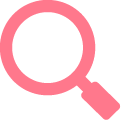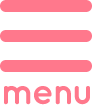必修予想問題
予想問題で必修問題対策。あわせて知っておきたい知識も解説!
- <no.20>抗アレルギー薬
- 抗アレルギー薬の作用はどれか。
- 抗血小板作用
- 抗ステロイド作用
- 抗ヒスタミン作用
- 抗プラスミン作用
解答3 抗ヒスタミン作用
1.× 抗血小板作用をもつのはアスピリンやチクロピジン塩酸塩などである。
2.× 抗アレルギー薬には抗ステロイド作用はなく、ステロイド薬はアレルギーの治療に使われる。
3.〇 抗ヒスタミン作用によってアレルギーの症状が抑えられる。他の抗アレルギー薬の作用機序にはケミカルメディエーター遊離抑制、抗ロイコトリエンなどがある。
4.× 抗プラスミン作用は止血剤のひとつであるトラネキサム酸(トランサミン)がもつ。
①ヒスタミンについて知ろう
タンパク質を構成する20種類のアミノ酸のひとつにヒスチジンがあります。食品中のヒスチジンは食品に存在するヒスタミン産生菌の作用により、ヒスタミンに変換されることがあります。
ヒスタミンは加熱でも効果を失わない性質があり、マグロ、カツオ、サバ、イワシ、サンマ、ブリ、アジなどの赤身魚に多く含まれます。食品を常温に放置する等の不適切な管理をすると、食品中のヒスタミン産生菌が増殖によってヒスタミンが生成されてしまい、食中毒の原因となります。
②ヒスタミンの作用を知ろう
ヒスタミンはアレルギー、炎症、胃酸分泌、神経伝達などに関係します。肥満細胞や好塩基球に貯蔵されていますが、IgEによる抗原抗体反応により細胞外に遊離します。組織では血管透過性の亢進や気管支平滑筋の収縮などが生じ、アレルギー疾患(蕁麻疹、気管支喘息、アレルギー性鼻炎など)を引き起こします。
③抗ヒスタミン薬について知ろう
細胞のヒスタミン受容体で覚えておきたいものに、H1受容体とH2受容体があります。アレルギー治療薬としての抗ヒスタミン薬とよぶのは、H1受容体拮抗薬(H1遮断薬)のほうです。抗ヒスタミン薬には抗コリン薬などと構造的に似ているため、鎮静、催眠、制吐作用などをもつものもあります。
H2受容体拮抗薬(H2遮断薬)は、H1受容体に影響することなく選択的に胃酸の分泌を抑制します。よって胃酸分泌を抑制する薬物として使われます。
〈引用文献〉
1.吉岡充弘 著者代表:系統看護学講座 専門基礎分野 疾病の成り立ちと回復の促進[3] 薬理学 第15版.医学書院,東京,2022.
2.薗田勝 編集:栄養科学イラストレイテッド 生化学.羊土社,東京,2017.
3.厚生労働省:ヒスタミンによる食中毒について.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130677.html(2023.11.8アクセス)
執筆:大塚真弓(看護師国家試験対策アドバイザー)